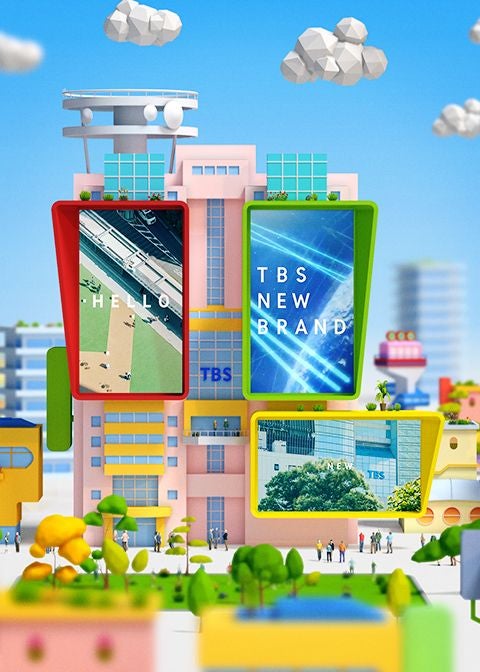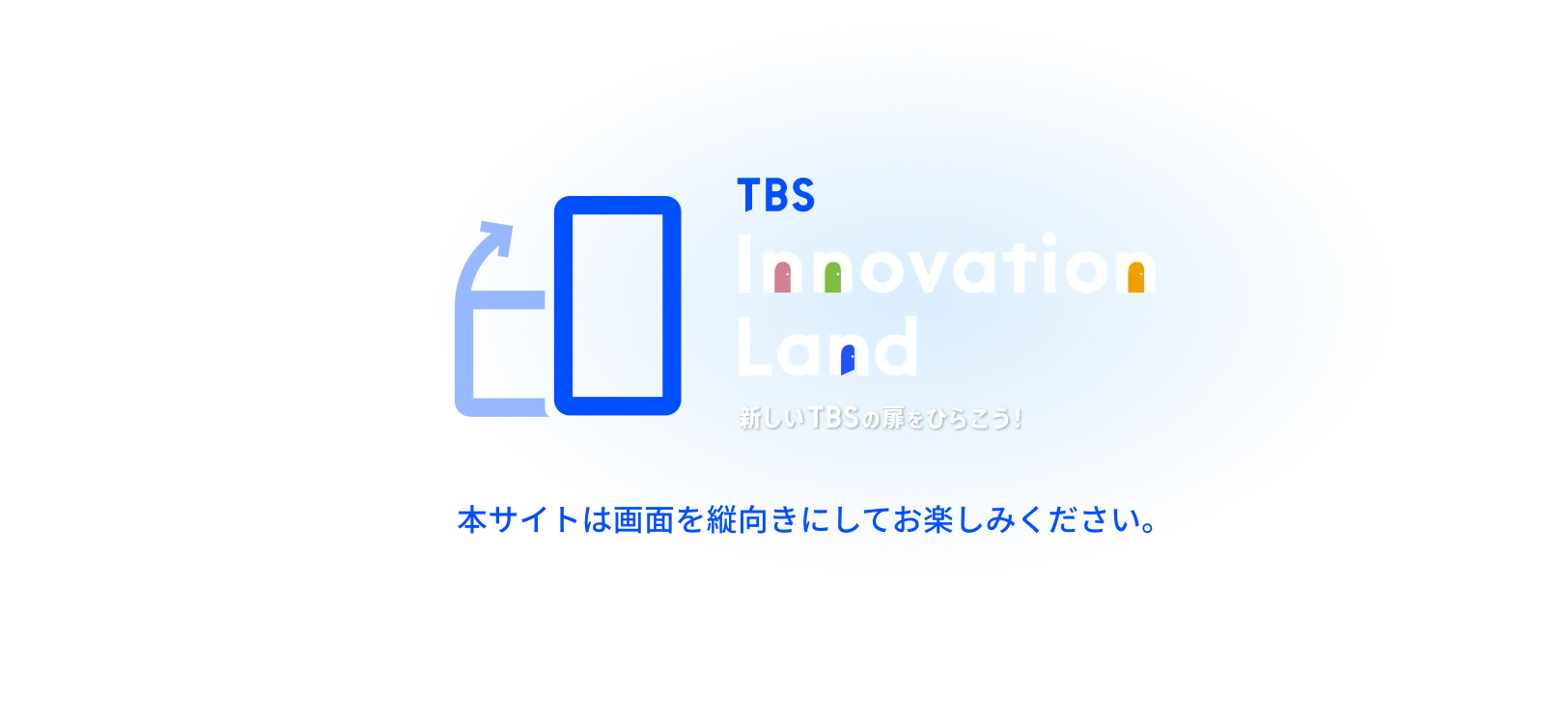- People
「今の自分の役割は悲劇を伝え続けること」戦場記者:須賀川拓が戦場に立ち続ける理由

JNN中東支局長の須賀川拓は、ガザ、ウクライナ、アフガニスタンの3つの戦地を取材。その様子がドキュメンタリー映画『戦場記者』として公開中です。映画の中のリアルな戦場は、私たちに戦争の残酷さを突きつけています。戦地取材にはどんな意図があったのでしょうか。そして、須賀川が戦場に立ち続ける理由とは?
映画『戦場記者』を作ることになった経緯は?
須賀川 実は、最初から理由があって映画にしたのではありません。誤解を恐れずに言うと、中東や戦地は非常に刺激的で興味深いテーマが多いので、取材中に「これは映画にできるかもしれない」と思ったんです。それでカメラ機材や照明も全部、最終的に映画になってもいいように切り替えました。時代背景や現地の人々の心情を伝える上で、映画は今後必要不可欠になっていくと思っています。
映画では3つの戦地を取り上げましたが、複数の戦場を取り上げた意図は?
須賀川 戦争の現場ってすごく遠く離れていますが、それぞれがどこかしら繋がっているんです。例えば、地域のパワーバランスが1ヶ所で崩れると、全然違う国のエネルギーの問題が起きたり、食料自給率の問題が起きたり、もしかしたら私達が住んでいる日本にも何らかの影響があるかもしれない。そう思ってほしくて、3つの地域を選びました。
映画を観ていただいたらわかると思いますが、いわゆる戦争指導者たち…軍や政治のトップである彼らの、言ってしまえば勝手な正義のぶつかり合いによって、結局割りを食っているのは関係のない庶民なんですよね。その政治的な判断に一切関与できない、ただ単に明日、美味しいパンを食べて子どもたちに平和に学校に行ってほしい、と思っている人たちの生活が奪われている。これは本当に全ての戦場において必ず共通していることなので、これもテーマとして絶対に伝えたいと思いました。
映画を観ていただいたらわかると思いますが、いわゆる戦争指導者たち…軍や政治のトップである彼らの、言ってしまえば勝手な正義のぶつかり合いによって、結局割りを食っているのは関係のない庶民なんですよね。その政治的な判断に一切関与できない、ただ単に明日、美味しいパンを食べて子どもたちに平和に学校に行ってほしい、と思っている人たちの生活が奪われている。これは本当に全ての戦場において必ず共通していることなので、これもテーマとして絶対に伝えたいと思いました。

双方が主張する正義のぶつかり合いを目の当たりにして、どう思いましたか?
須賀川 すごくシンプルに言うと、溝が深すぎて、お互いの主張を聞いても、「もうこれは歩み寄る余地がないんじゃないか」と絶望してしまうことは結構あります。
映画の中で特に見てほしいのは、ハマスとイスラエル軍の広報官トップのそれぞれのインタビューです。イスラエル側に一体どんな正義があって、なぜそういうことをしてるのか、ちゃんと彼らの意見を聞かなくちゃいけない。そうすると実は見えてくるのが、ハマスもハマスで勝手なことを言っている。インタビューのやりとりを見て、それぞれの主張に善悪のバランスが存在してることをぜひ感じてほしいと思います。
『戦場記者』というタイトルにはどんな思いがありますか?
須賀川 本来であれば私たち取材者ではなく取材対象者が主役なので、自分が主役になるのは非常にモヤモヤするし、実際に今もモヤモヤしています。しかし、結果的に自分が軸になることでいろいろな地域の戦争を全部繋げることができた。被害者の声を一つの軸でまとめてお伝えすることができたのは良かったと思います。
一言で言うと、「忘れないでくれ。僕たちのことを忘れないでくれ。」という思い。本当にそれがすべてだと思うんですよね。だからこそいきなり子どもやパートナー、友人を亡くして未来の希望もない絶望の中、僕らの向けたマイクに声を大きくして喋ってくれる。その言葉を託されたっていう気持ちにはなるんですよね。
やっぱり僕らは極めて失礼なことをしているわけで、それを忘れないためにも、自分への戒めの言葉でもありますけど、取材し続けなくちゃいけないですし、僕らが取材して報じなければ、当然視聴者の皆さんには情報が届かないですから。だからこそ続けていかなければならないと感じます。

映画をご覧になった観客からの感想を受けて、どんな気持ちですか?
須賀川 「100人見たら100通りの見方がある」という感想は非常に印象的でした。現場のニュースは白黒はっきりと判断できるものではない。だから、この映画を観て、パレスチナに思いを馳せる人がいてもいい、イスラエル側に思いを馳せる人がいてもいい、そうやって話が盛り上がることが何よりもまず重要だと思います。今回この映画はそのきっかけになってほしいと思って作ったので、この感想はありがたかったです。
戦場には世界中のジャーナリストが集まると思いますが、海外のジャーナリストとの交流を通して気付いた点はありますか?
須賀川 日本は「自己責任論」という言葉があるように、戦場に行くと私も直接批判を受けてしまうのですが、海外の人たちは逆なんですよ。「なんであんたらは戦地に行かないんだ?」という批判があります。そこは圧倒的に視聴者の意見が真逆だと感じました。だからこそ彼らは、戦地の一番危険なところに突っ込んでいくのです。僕も突っ込んでしまうタイプなので、取材クルーには「危ないと思ったら喧嘩してでも止めてくれ」と言っています。実際、アフガニスタンでも3回くらい大喧嘩しました。僕はどうしても行きたいところがあって、2回行った場所があるんですが、「まだ撮り足りてないからどうしても行く」と言ったら朝から大喧嘩。クルーの判断が正しかったかはわかりませんが、僕はクルーの中に1人でも嫌だと思った人がいたら行かないと決めているので、行きませんでした。安全を担保するというのは、そういった判断の積み重ねなのかなと思います。

これからも危険な戦地には足を運ぶと思いますが、記者として、そして映画監督としてどんな思いで現地に立ちたいですか?
須賀川 僕らの報道は、今起きている戦争を食い止めることに関しては非常に無力だと思います。ですが、その悲劇をちゃんと伝える、伝え続けることによって、もしかしたら将来的に紛争を一つでも二つでも減らすことができるかもしれない。難民を1人でも2人でも助けることができるかもしれない。その可能性があるのなら、この仕事はずっとやり続ける価値があるし、やり続けなくちゃいけないと感じています。現地に通い続けて、その都度拾った物語を伝え続ける。それが今の自分の役割なので、続けていきたいと思います。
須賀川拓(TBSテレビ報道局中東支局長)
2006年入社。スポーツ局配属。2010年10月報道局社会部、「Nスタ」を経て、現職(JNN中東支局長)。担当した主な作品は、「大麻と金と宗教~レバノンの“ ドラッグ王 ”を追う」、ガザの起業家に密着した「天井の無い監獄に灯りを」、戦争犯罪を追及する「戦争の狂気 中東特派員が見たガザ紛争の現実」。その他にも、ベイルート港の大爆発後メディア初となる爆心地取材や、タリバン幹部への直撃インタビューで話題を呼んだ。。最近はテレビでは伝えきれない紛争地の生の空気をTBS公式YouTubeで積極的に配信している。2022年、国際報道で優れた業績をあげたジャーナリストに贈られる「ボーン・上田記念国際記者賞」を受賞。
■TBSドキュメンタリー映画「戦場記者」https://senjokisha.jp/
(本記事は「TBSレビュー」(1/8放送)をもとに再構成しました)